九州北部でこんなに雪が積もるなんて!
日曜日は、マンションのベランダからみた外が一面の銀世界であることに、かなり興奮した。
こんなことは、一生に一度かもしれないな、と。
しかし、月曜日、仕事となると、様相が一変する。
出勤しなければならない状況では、雪というのは、とんでもない障害物だったのだ。
そもそも、九州は、山間部でもなければ、雪に対する備えという概念に乏しい。
ちょっと積もっても、朝になってしばらくすれば、土色になった雪の残骸が道路脇にあるくらい、だと思っていた。
結局、いつ来るかわからな電車を待ち、遅刻してしまったのだが、仕事先はそんなにたいして積もってもおらず、「そんなに大変だったんですか?」と怪訝な顔で見られてしまった。
そして今日、車の雪を払って、出勤したのだが、これがまたとんでもないことに。
相変わらず高速は通行止めで、一般道を通っていたら、比較的大きな道路の一部に集中して雪が残って、道がガタガタになり、スタック(雪やぬかるみにタイヤがはまって、動けなくなる状態)する車が続出していたのだ。
動かない車のなかで様子をみていると、目の前の工場の従業員とおぼしき男たちが、動けなくなってしまった車に駆け寄って、車を救出してあげていた。
ああ、知り合いの車だったんだな、と思っていたら、その人たちは、次から次へと、スタックしている車を見つけては駆け寄って、助け続けていたのだ。
目の前の道路が塞がってしまうと困るし、今日はこの雪で仕事にもならないから、ということだったのかもしれないけれど、彼らにとっては、ほとんど何のメリットにもならないであろう行為を、淡々と、ひたすら続けているのをみていたら、なんだか、人間って、そんなに捨てたものでもないんじゃないか、という気分になってきて。
いや、もちろん僕だって、普段から人間に絶望しまくっているわけでもないし、人は状況によって、善人にも悪人にもなりうることは知っているつもりだ。
でも、こうして雪の日の朝に、困っている人たちを淡々と助けている彼らの姿をみて、「ああ、こういうのが、『ライ麦畑のキャッチャー』なのかな、なんて実感したのだ。
助けられた多くの車は、彼らにお礼も言わずに、その場を去っていく。
そもそも、いちいち車からおりてお礼を言っていたら、さらに酷い渋滞になってしまうだろうし。
彼らも、そんなお礼などは期待していないように、ひと仕事を終えたら、振り返りもせずに、すぐに次の車のところに向かっていた。
まあ、そんなことを高みの見物的に考えていたら、僕の車もスタックしてしまい、助けていただいて、お恥ずかしい限りでした。
あのとき、窓を開けて簡単にお礼を言うことしかできなくて、すみません。
こんな雪の朝に出勤しなくても良い世の中であるべきなのだろうし、僕も車での移動は避けるべきだった。反省しています。
寒い中、淡々と、もう二度と会わないかもしれない人々を助け続けたあなたたちの姿をみて、僕もそういう人間でありたいな、と思ったのです。
本当に、ありがとうございました。
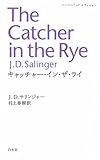
キャッチャー・イン・ザ・ライ (ペーパーバック・エディション)
- 作者: J.D.サリンジャー,J.D. Salinger,村上春樹
- 出版社/メーカー: 白水社
- 発売日: 2006/04
- メディア: 新書
- 購入: 11人 クリック: 73回
- この商品を含むブログ (188件) を見る




